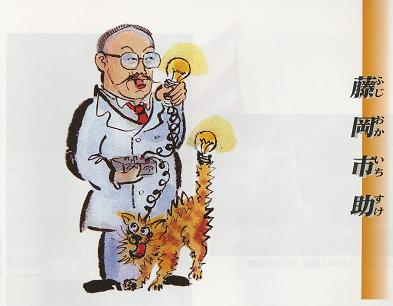 岩国市内を走っている赤いレンガ色のバス「いちすけ号」を皆さんご存知ですね。あれは明治42年(1909年)、藤岡市助が中国地方で初めて新町と岩国駅の間を走らせた電車を記念して復元したものです。もっとも電車とバスの違いはありますが・・・・。藤岡市助は安政4年(1857年)3月14日、岩国藩士であった藤岡喜介の長男として生まれました。慶応元年(1865年)、8歳の時岩国藩の藩校「養老館」の素読寮に入学し、14歳になって岩国兵学校に入り、イギリス式の軍隊教育を受けています。明治7年(1874年)17歳になった市助は、旧藩主の吉川経健(つねたけ)の命令を受けて、東京に遊学しました。そして、工務省の工学寮に合格し、電信科の第3期生となりました。ここからが、市助の電気との係わりです。在学中、市助はエアトン教授の指導の下下に工務省中央電信局が完成したお祝いに、グローブ電池50個を使って、デュボスクのアーク灯を灯しました。これが日本最初の電灯で、この点灯された3月25日が、現在、電気記念日になっています。このほか、市助は日本で最初に発電機や白熱灯を作ったり、日本で初めて東京の上野で電車を走らせたりしています。明治23年(1890年)には、日本初のエレベータの設置(この日11月10日はエレベータの日)など、藤岡市助は、電気を通じて日本の近代化に貢献しました。
岩国市内を走っている赤いレンガ色のバス「いちすけ号」を皆さんご存知ですね。あれは明治42年(1909年)、藤岡市助が中国地方で初めて新町と岩国駅の間を走らせた電車を記念して復元したものです。もっとも電車とバスの違いはありますが・・・・。藤岡市助は安政4年(1857年)3月14日、岩国藩士であった藤岡喜介の長男として生まれました。慶応元年(1865年)、8歳の時岩国藩の藩校「養老館」の素読寮に入学し、14歳になって岩国兵学校に入り、イギリス式の軍隊教育を受けています。明治7年(1874年)17歳になった市助は、旧藩主の吉川経健(つねたけ)の命令を受けて、東京に遊学しました。そして、工務省の工学寮に合格し、電信科の第3期生となりました。ここからが、市助の電気との係わりです。在学中、市助はエアトン教授の指導の下下に工務省中央電信局が完成したお祝いに、グローブ電池50個を使って、デュボスクのアーク灯を灯しました。これが日本最初の電灯で、この点灯された3月25日が、現在、電気記念日になっています。このほか、市助は日本で最初に発電機や白熱灯を作ったり、日本で初めて東京の上野で電車を走らせたりしています。明治23年(1890年)には、日本初のエレベータの設置(この日11月10日はエレベータの日)など、藤岡市助は、電気を通じて日本の近代化に貢献しました。
 明治17年(1884年)、27歳の時、市助は10歳年上のトーマス・エジソンを研究室に訪ね、彼の発明品に感嘆しました。そして彼から励まされ、翌年には市助のいた工部大学に電信機と白熱灯を贈られました。大正7年(1918年)60歳で永眠。墓は東京にありますが、錦見の妙覚院にもあります。
明治17年(1884年)、27歳の時、市助は10歳年上のトーマス・エジソンを研究室に訪ね、彼の発明品に感嘆しました。そして彼から励まされ、翌年には市助のいた工部大学に電信機と白熱灯を贈られました。大正7年(1918年)60歳で永眠。墓は東京にありますが、錦見の妙覚院にもあります。
出典: -郷土の誇り- 岩国偉人伝
岩国中央ロータリークラブ発行
伝記を読んだ感想はこちらへ

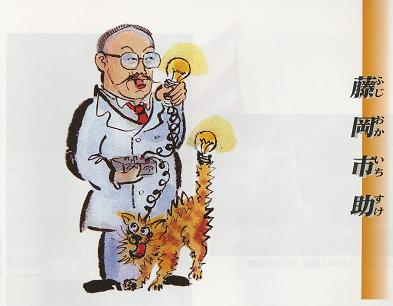 岩国市内を走っている赤いレンガ色のバス「いちすけ号」を皆さんご存知ですね。あれは明治42年(1909年)、藤岡市助が中国地方で初めて新町と岩国駅の間を走らせた電車を記念して復元したものです。もっとも電車とバスの違いはありますが・・・・。藤岡市助は安政4年(1857年)3月14日、岩国藩士であった藤岡喜介の長男として生まれました。慶応元年(1865年)、8歳の時岩国藩の藩校「養老館」の素読寮に入学し、14歳になって岩国兵学校に入り、イギリス式の軍隊教育を受けています。明治7年(1874年)17歳になった市助は、旧藩主の吉川経健(つねたけ)の命令を受けて、東京に遊学しました。そして、工務省の工学寮に合格し、電信科の第3期生となりました。ここからが、市助の電気との係わりです。在学中、市助はエアトン教授の指導の下下に工務省中央電信局が完成したお祝いに、グローブ電池50個を使って、デュボスクのアーク灯を灯しました。これが日本最初の電灯で、この点灯された3月25日が、現在、電気記念日になっています。このほか、市助は日本で最初に発電機や白熱灯を作ったり、日本で初めて東京の上野で電車を走らせたりしています。明治23年(1890年)には、日本初のエレベータの設置(この日11月10日はエレベータの日)など、藤岡市助は、電気を通じて日本の近代化に貢献しました。
岩国市内を走っている赤いレンガ色のバス「いちすけ号」を皆さんご存知ですね。あれは明治42年(1909年)、藤岡市助が中国地方で初めて新町と岩国駅の間を走らせた電車を記念して復元したものです。もっとも電車とバスの違いはありますが・・・・。藤岡市助は安政4年(1857年)3月14日、岩国藩士であった藤岡喜介の長男として生まれました。慶応元年(1865年)、8歳の時岩国藩の藩校「養老館」の素読寮に入学し、14歳になって岩国兵学校に入り、イギリス式の軍隊教育を受けています。明治7年(1874年)17歳になった市助は、旧藩主の吉川経健(つねたけ)の命令を受けて、東京に遊学しました。そして、工務省の工学寮に合格し、電信科の第3期生となりました。ここからが、市助の電気との係わりです。在学中、市助はエアトン教授の指導の下下に工務省中央電信局が完成したお祝いに、グローブ電池50個を使って、デュボスクのアーク灯を灯しました。これが日本最初の電灯で、この点灯された3月25日が、現在、電気記念日になっています。このほか、市助は日本で最初に発電機や白熱灯を作ったり、日本で初めて東京の上野で電車を走らせたりしています。明治23年(1890年)には、日本初のエレベータの設置(この日11月10日はエレベータの日)など、藤岡市助は、電気を通じて日本の近代化に貢献しました。 明治17年(1884年)、27歳の時、市助は10歳年上のトーマス・エジソンを研究室に訪ね、彼の発明品に感嘆しました。そして彼から励まされ、翌年には市助のいた工部大学に電信機と白熱灯を贈られました。大正7年(1918年)60歳で永眠。墓は東京にありますが、錦見の妙覚院にもあります。
明治17年(1884年)、27歳の時、市助は10歳年上のトーマス・エジソンを研究室に訪ね、彼の発明品に感嘆しました。そして彼から励まされ、翌年には市助のいた工部大学に電信機と白熱灯を贈られました。大正7年(1918年)60歳で永眠。墓は東京にありますが、錦見の妙覚院にもあります。